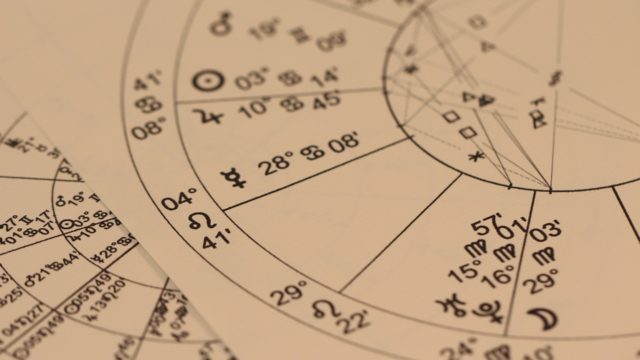月5000円の積み立てから始めた裕二はその後着々とお金を貯め、しかも貯めるばかりではなく生活も楽しみ、響子との愛を育んでいった。
そして月日は流れ、ようやく100万円が貯まった。
「やればできるじゃん、俺。」
通帳を記帳して、裕二はニヤニヤしていた。
100万円貯まったら響子にプロポーズすることを決めていた。
しかし、はたと気づいた。
あれ、指輪っているよね。
指輪のお金も必要なのか?
・・・そんなことしてたら、一体いつプロポーズできるんだろう。
親父に相談しよう。
「我が息子ながら何をやっているんだ。」
裕二の父は、息子の迷走ぶりに呆れていた。
「とにかく婚約指輪はお前の貯金で買え。結納金はうちで用意してやる。」
「えっ父さんありがとう!」
裕二は泣きそうになった。
「ところで響子さんはプロポーズ受けてくれるんだろうな。」
「ま、まさか。大丈夫だよ。」
と言いながら、ちょっぴり不安だった。

「とても眺めがいいわね。そして美味しい。」
裕二と響子は、春吉の博多ミツバチで食事をしていた。
中洲の夜景を一望できる、リバーサイドのダイニングバーである。
食事の後、裕二はプロポーズをする予定だ。
お店には、今日プロポーズをするので、彼女が「はい」と言ったら一旦照明を落としてもらって、おめでとうございますと言ってもらい、シャンパンを抜いてもらう手はずになっている。
裕二はお店のマネージャーに目配せした。
そして姿勢を正し、
「響子ちゃん、僕と結婚してください。」
と言って小さな箱を響子に差し出した。
裕二が必死に貯めて買った婚約指輪だ。
響子は驚き、裕二を見つめて言った。
「裕二くん、これ、キャッシングで買ったんじゃないよね。」
一瞬場の空気が止まり、裕二もお店のマネージャーも、どうしていいかわからなかった。
「もちろん。こつこつ貯めて買ったんだよ。」
「嬉しい。」
響子は泣きだした。これってOKってこと?
裕二はマネージャーを見て頷いた。
お店の照明が一瞬落とされ、次の瞬間
「おめでとうございます!」
という声とともにポン、とシャンパンの栓が勢いよく飛んだ。
響子はその演出に驚きながら、涙をふき、
「一緒に歩いていこうね。」
と言った。
ついていくんじゃなくて、一緒に歩くんだ。ずっとね。
「この後、ママのところに報告に行こうよ。」
「もちろん。ママ、喜ぶと思うわ。松田さんも。」
ママに叱られて、お金を貯めはじめて、この日が来た。ママ、ありがとう。
おわり。